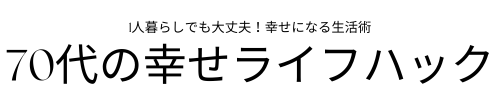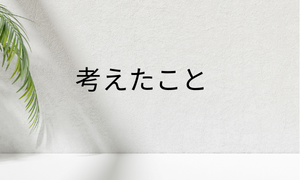にほんブログ村読む時はこのブログ村をポチってね!
先日のブログで触れた「時分の花」と「まことの花」について、考えたことを書いてみました。
「時分の花」と「まことの花」という言葉は、世阿弥が残した花伝書(「風姿花伝」)に書かれていた言葉で、『若い演者(能楽師)が、その時の人気や力量(「時分の花」)を本当の力(「まことの花」)と思い、努力や研鑽を怠れば本当の力(「真実の花」)を手に入れることは出来ないだろう』という言葉によるものです。
私は中学の1年生から、学校の仕舞部を通して、個人的にも金春流の師範だった秋山邦子先生の師事を受けてきました。
秋山先生は、お母様が九条家の出ということもあり、金春流の当時の名人であった桜間金太郎(後の弓川きゅうせん)さんの直弟子であったということでした。
実際、先生の舞は品格があり、戦後の不遇な生活を舞という自己の力で切り抜けて来たという誇りさえ感じさせるものでもありました。
能舞台では能舞台の大きさで、6畳間では6畳間に見合う大きさで、豊かに大きく舞うようにしなさいと教えられたものでした。
その秋山先生が、弓川先生亡き後の当代(昭和)の名人と、何度も話されていたのが桜間道雄さんのことでした。
私がお話を聞いた頃には桜間道雄さんは高齢になっていて、品のある枯れた能は既に別格のものとされていました。
けれども、私の心を捉えた演目は「野宮」や「卒塔婆小町」と言った枯れたものではなく、秋山先生の話される「道成寺」だったのです。
歌舞伎は、能を庶民にも楽しめるように分かりやすい表現に直したものですから、能の表現が所々に見られます。
歌舞伎でも、白拍子の花子が拍子を踏みますよね。あれは、能では「乱拍子」と言って爪先や踵を上げ下げした独特の拍子を小鼓との緊迫した間を持って踏み鳴らす、息を呑むような見せ場のひとつなのです。
僧安珍に対する執着から蛇霊に変わってしまう清姫が、鐘楼への階段を一歩また一歩と踏み締めながら、蛇霊への生成りを果たしていく姿があの乱拍子には込められているのです。
そして拍子が踏み鳴らすような速さとなり、鐘楼を駆け上がっていく様を表すと共に、舞は「急の舞」から「急急の舞」へと変わり、シテは釣鐘を手で指すと見るやくるりと回転しながら飛び上がり、同時に釣鐘が落とされてシテは鐘の中に…という見応えのある演出になっていたのだそうです。
能面は人の顔よりも一回り小さく出来ています。それはシテのあごの部分が首に見えるようになっているからだそうで、それゆえ目の穴は普通のお面よりも上の額の辺りに当たることとなります。
そのためシテは目の見えない状態で舞うこととなり、全ては勘と身体が覚えている舞台の記憶で舞っている状態となるのです。
舞台のクライマックスである「鐘入り」は、このようなシテが勘を頼りに鐘の下で飛び上がると同時に張子の鐘が落ちるという演出ですから、その難しさは想像を絶するほどだったのではないでしょうか。
その上、落ちる鐘の下から飛び上がるシテの足が覗くようでは不調法な失敗なのだそうで、シテが鐘の中に吸い込まれるように消えるのが名人の技なのだということでした。
張子とはいえ、かなりの重さがある鐘が落ちると同時に飛び上がるのですから、シテは強かに頭を打つことになり、気を失う人もいたという話でした。
繰り返し話される道成寺の演出に魅了されて、私は、いつか縁があれば桜間道雄さんの道成寺を見たいものだと思い続けていたのです。
願い叶って、後年、亡くなる前の桜間道雄さんの道成寺を観る僥倖を得ましたが、その時の演出は年齢の事もあり、上げた両の手で釣鐘を触り、その後、膝をついて中啓を逆に立てた姿での鐘入りとなりました。
素晴らしい能であり、二度と目にできないものではありましたが、それでも矢張り秋山先生が熱を込めて語っていらした鐘入りを観たかった…というのが本心でした。
このように「まことの花」は素晴らしいものであることは確かだと思いますが、それでも壮年の華やかな「時分の花」には、その時でなければ見ることの出来ない得難い美しさがあるのだと、今回しみじみ思い出した次第です。
能楽と同様、歌舞伎においても若く美しく力量のある役者がその時の全ての輝きを放って演じる「時分の花」には、矢張り見逃すことの出来ない得難い美しさがあるのではないでしょうか…?